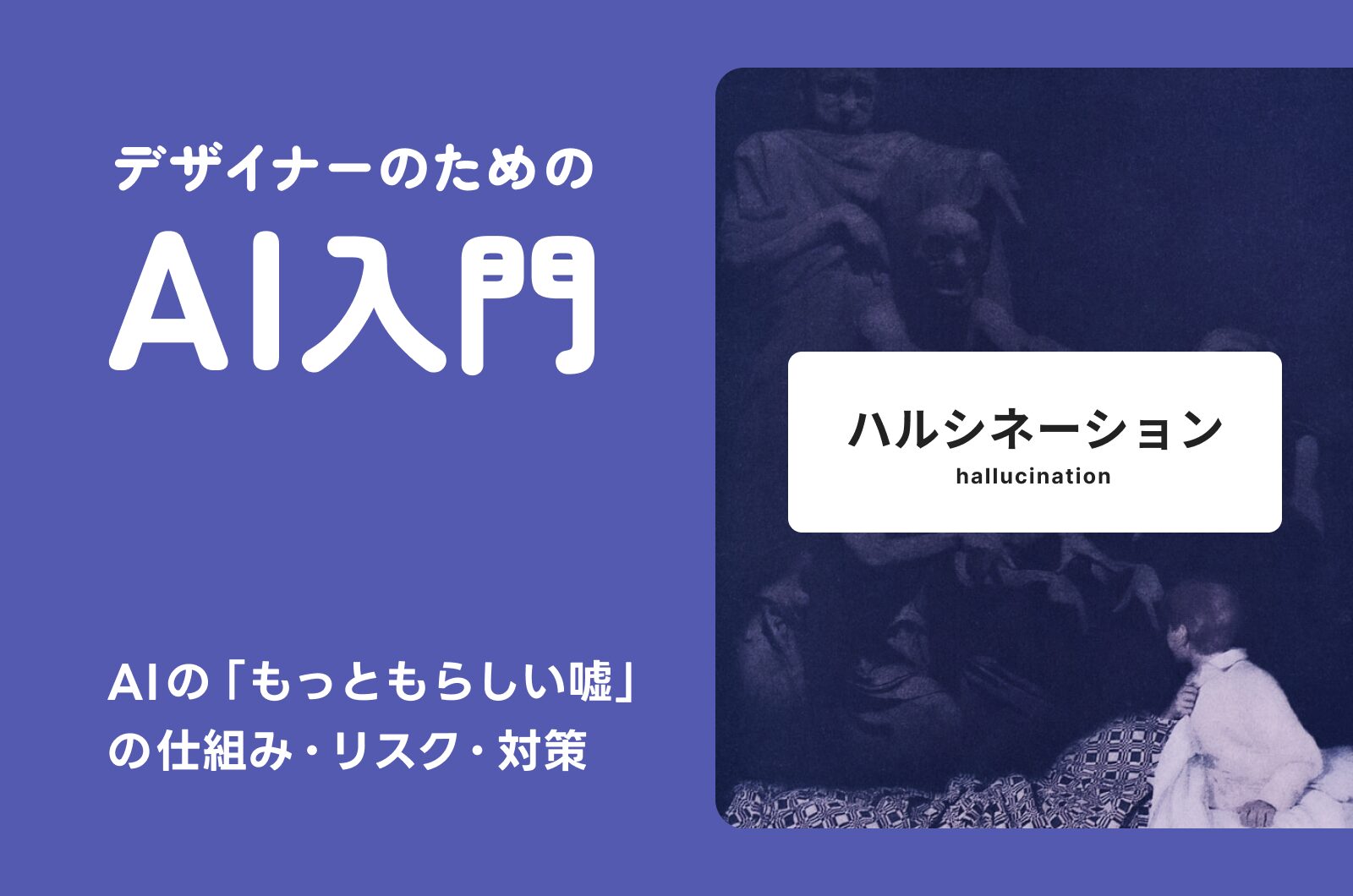デザイナーとして働いていると、さまざまな課題に直面しますよね。
品質管理の問題、クライアントやステークホルダーとの認識のズレ、プロジェクトの方向性への疑問⋯。こうした課題を前に、「自分が頑張ればなんとかなる」「自分の力不足かもしれない」と、一人で抱え込んでしまうことはありませんか?
デザイナーが抱える課題の多くは、個人で解決しようとするのではなく、組織・チーム全体の問題として捉えることも大事になってくると私は思っています。
なぜ「私たち」の問題として捉えることが重要なのか?
デザイナー一人が声を上げても、「個人の不満」「デザイナーの感覚的な意見」と思われてしまうことがあります。
特に経営層や他部署との間では、デザインの専門性が理解されにくく、意見が軽視されがちです⋯(悲しい)。
ですが、デザイナー個人ではなく、デザイナー自身も視座を広げてチーム全体の課題として提示することで、経営層も無視できない問題として認識してもらえます。
複数の部署が影響を受けている、組織の成果に関わる、といった視点で伝えることで、建設的な議論が可能になり、根本的な解決につなげることができます。
デザイナーのあるあるなケースと考え方
デザイナーさんからよく聞く、2つのあるなるなケースと、私の過去の経験からの考え方を挙げてみます。
ケース1:品質管理の課題を「私たち」の問題にする
制作物の品質が期待値に届かず、結局デザイナーが細かく修正・チェックせざるを得ない。
そんな状況に悩むデザイナーは少なくありません。(もちろん私も例外なく。)
「関係性もあって言いにくい」「自分が手を動かせばいい」と、一人で負担を抱えてしまいがちです。
こうした場合、まず影響を受ける他部署の担当者と話してみることも有効だったりします。制作物の品質は他部署の業務やブランドイメージにも影響するため、複数の担当者が同じ課題を感じている可能性があります。
そして、デザイナー個人の意見ではなく、「私たち」として共通の問題として経営層に伝える。そうすることで、責任の所在が明確になり、品質管理の体制づくりや見直しを含めた建設的な議論ができるようになります。
ケース2:施策の課題を組織全体で振り返る
施策を実施したものの、期待していた結果が得られず、目的を達成できなかった。
こうした経験を持つデザイナーさんも多いのではないでしょうか。
施策に課題があることはわかっていても、統括している担当者にどうアプローチすればいいのか悩んでしまうことがあります。
こうした場合、施策の設計は、マーケティング、営業、デザイン、開発など複数の部署が関わっているはずです。デザイナーだけが反省するのではなく、組織全体の振り返りの機会を設けることで、企画段階からの課題が見えてきたりします。
全員が当事者意識を持つことで、「次回は企画段階でターゲット像をもっと明確にしよう」「効果測定の指標を事前に決めよう」といった具体的な改善策が生まれ、組織として成長する機会になるんですね。
組織・チームで前に進むための、3つのヒント
改めて、これらのケースから見えてくる、実践的なヒントをまとめてみます!
ヒント1:関係者の中から味方を見つける
課題を感じたら、まず影響を受ける他部署の担当者など、味方を見つけましょう。自分だけが感じている問題なのか、それとも他の人も同じように感じているのか。共通の問題認識を持つことで、提案の説得力が増します。

↑ こんな感じで私も全職種対象の社内ミニワークショップを企画・実施したことがあります。就業後の参加は難しいという方もいるので、みんなが参加しやすいようにお昼に40分だけという形でやりました。
ヒント2:「私たち」の視点で伝える
上層部に伝える際は、「私は困っている」ではなく、「私たちのチームではこういう課題があり、こう改善したい」という視点で考え、話してみましょう。個人の不満ではなく、組織の成果に関わる問題として提示することがポイントです。
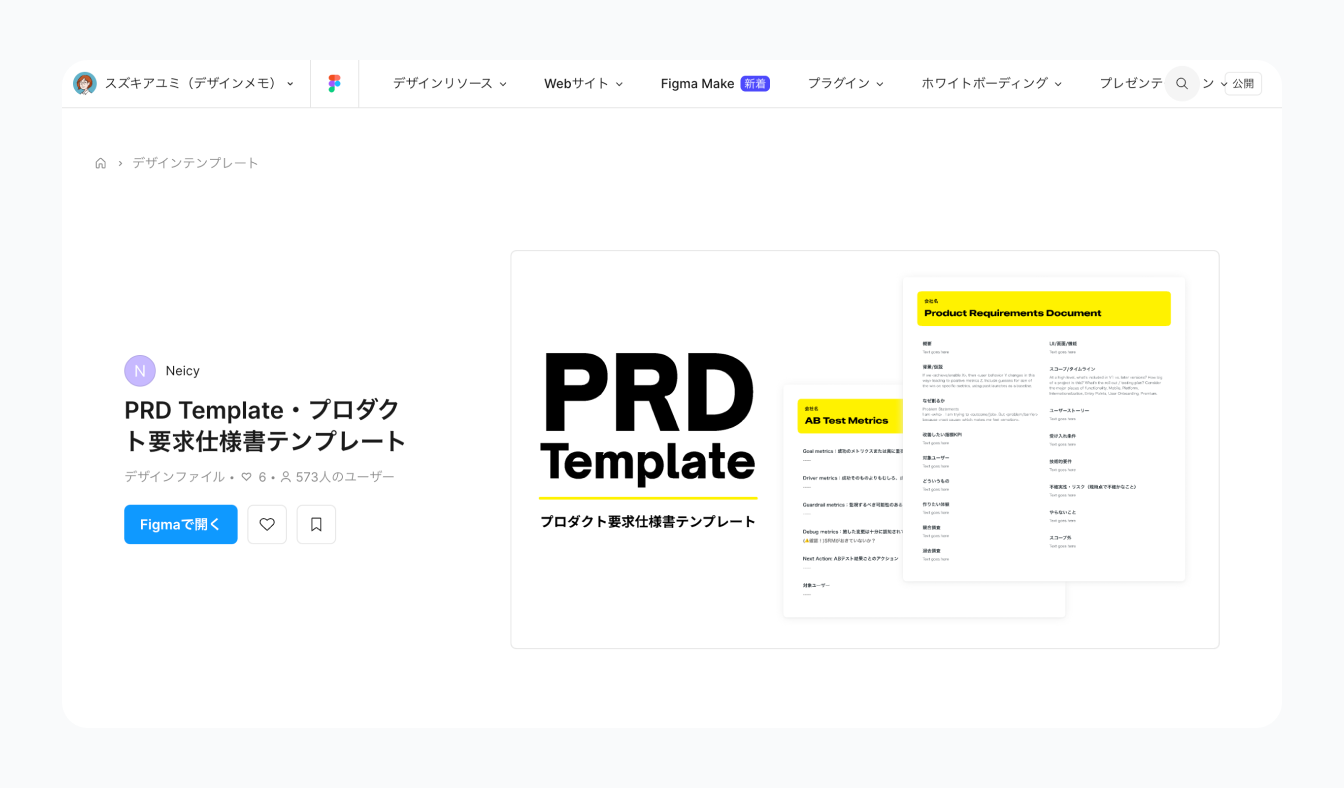
↑ フォーマットとしておすすめなFigmaプラグイン:PRD Template・プロダクト要求仕様書テンプレート
ヒント3:振り返りの場を設けて共通認識にする
プロジェクト後には、関係者全員で振り返りの場を持つものオススメです。
成功も失敗も共有し、「次はどうするか」を一緒に考える文化を作ることで、デザイナーが一人で抱え込む状況を防げます。
私も実際にチームで活用したことがありますが、シンプルなフレームワークで、誰でも取り組みやすいのがよいところです。
- Keep(続けること):うまくいったこと、今後も続けたいこと
- Problem(問題点):うまくいかなかったこと、課題に感じたこと
- Try(試すこと):次回改善したいこと、新しく挑戦したいこと
この3つの視点で振り返ることで、チーム全体で具体的な改善アクションが見えてきます。

(Keepで褒め合うのもめっちゃ大事です⋯!)
最後に、デザイナーも組織を動かす力を持っている
デザインの課題解決には、個人の努力だけでなく、「私たち」の視点でチーム全体を巻き込み、組織として取り組む姿勢を作ることも大切だと思います。
デザイナーは、ユーザーの視点に立ち、課題を可視化し、解決策を提示するプロフェッショナルです。その力は、プロダクトやサービスだけでなく、組織の課題解決にも活かせるはず⋯!
一人で抱え込まず、周りを巻き込んで、組織・チーム全体で前に進む。
時間がかかることではありますが、デザイナーとして自分が働きやすい環境づくりという意味でも、まずはちょっとずつ取り組んでみるのはいかがでしょう?(もちろん、休息も忘れずに!)

- ゆるく参加できるサードプレイスはいかがでしょうか?デザインメモ運営:みんなのデザインメモ